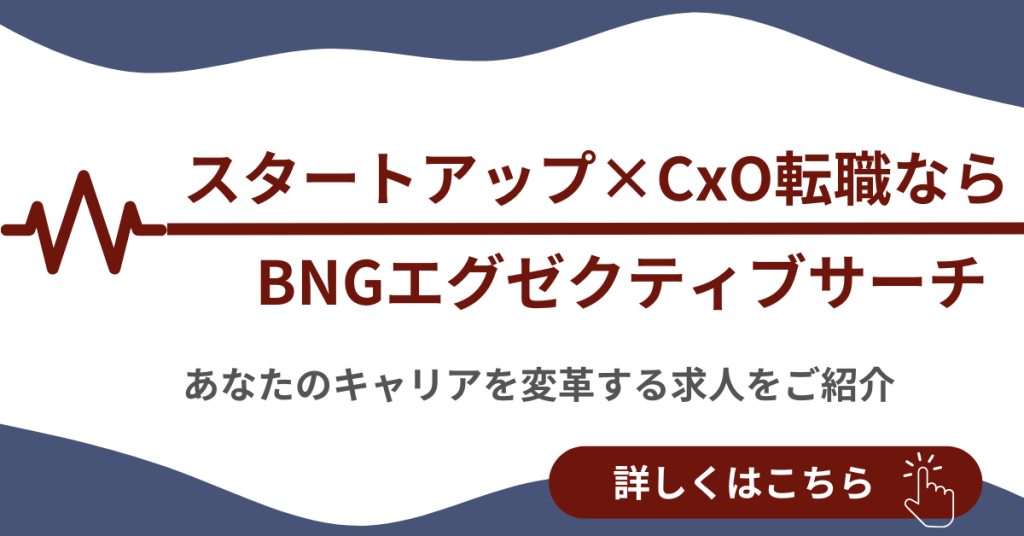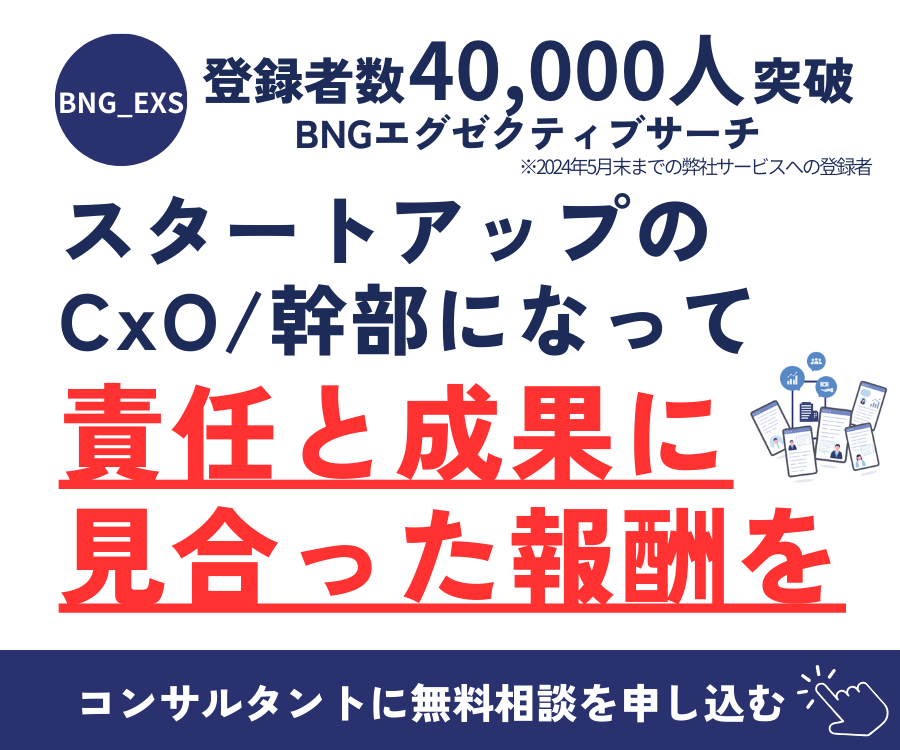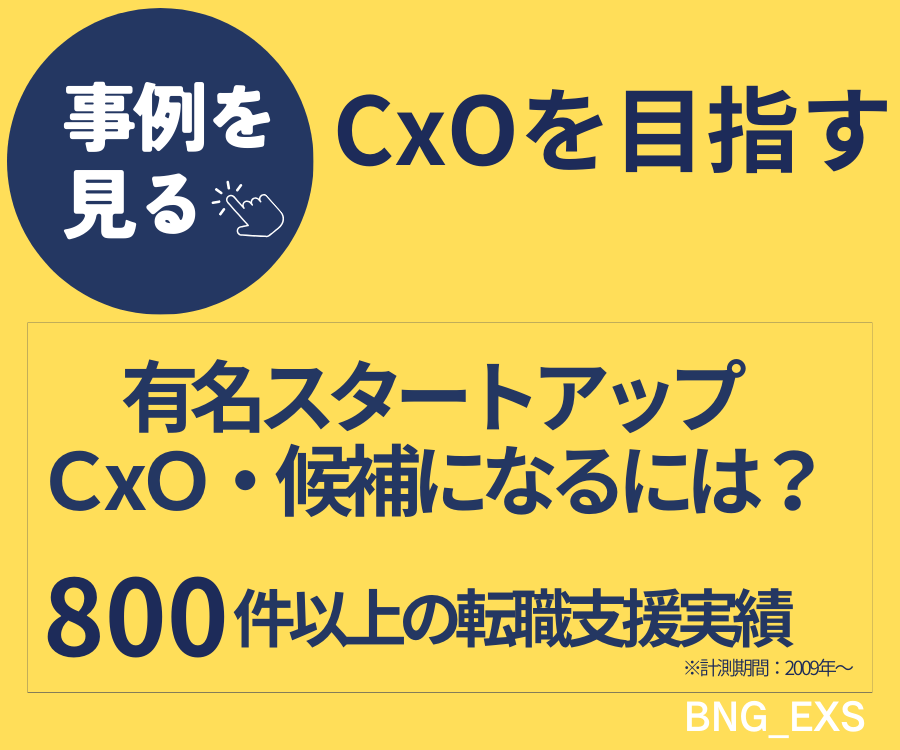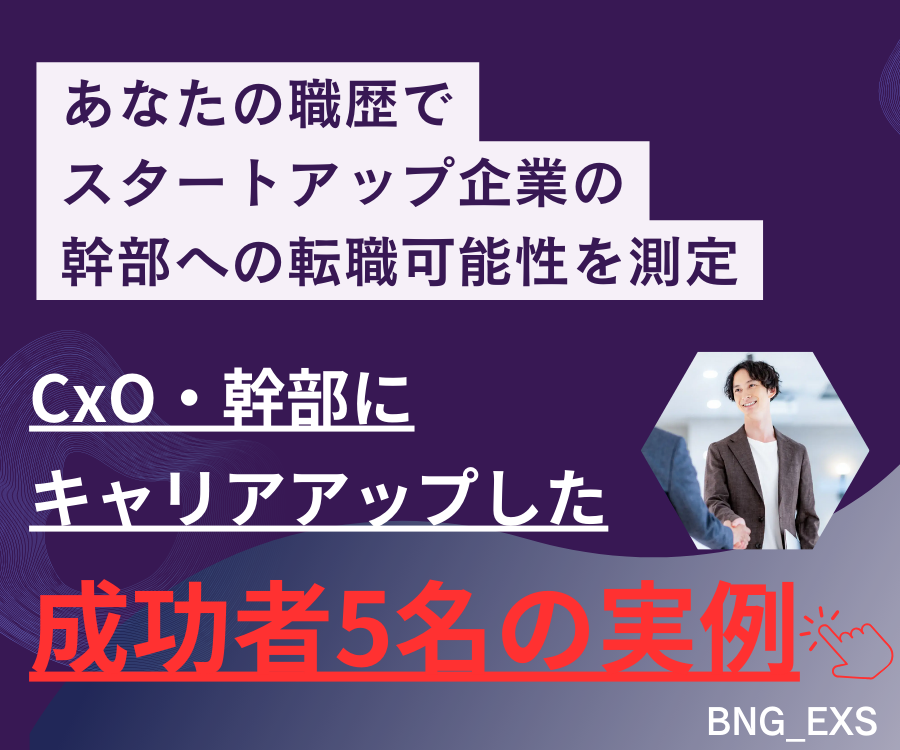部長の役割は、企業の各部署の責任者として、企業戦略に影響する重要な意思決定を行うことです。本記事では、多くの企業において「上級管理職」と位置付けられている部長職の定義から具体的な役割、課長との違いなどについて解説します。
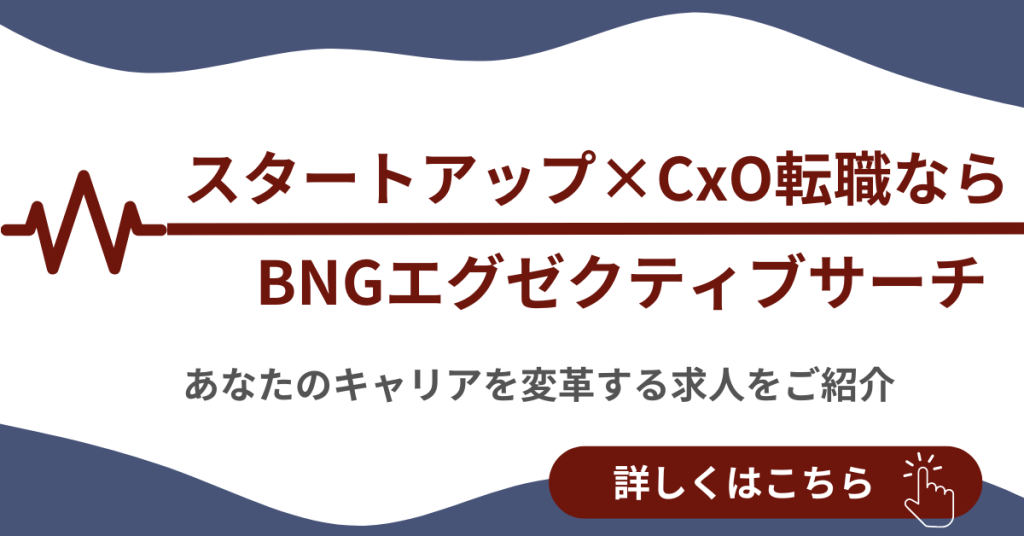
スタートアップのCxO/幹部になって責任に見合う報酬を!
登録者数40,000人突破したBNGエグゼクティブサーチでは、スタートアップのCxO/幹部になって責任と成果に見合った報酬を獲得したキャリアアップ事例をご紹介しています。コンサルタントへ...
そもそも部長職とは?
部長は、多くの企業において「上級管理職」との位置付けをされています。取締役など経営陣の重要な経営判断をサポートする存在として、企業の経営の一部分を担う役割を有しているのが部長職の特徴です。
役割その1:企業の成長に貢献
複数の課を統括する部門の長として、部長には「ヒト・カネ・モノ」といった経営資源を上手に評価・活用し、確実に収益を上げて企業の成長に貢献することが求められます。
役割その2:経営陣のサポート
経理や人事部門のトップである部長は、取締役などの経営陣から専門分野のプロとしてさまざまな意見を求められる場面があります。また経営陣の代理としてそれぞれの部署でビジョンを語り、組織を強化することも重要な役割のひとつです。
役割その3:新しい価値の創造
部長は自分の部署を多角的に観察し、必要に応じて組織や仕事のやり方を見直す必要があります。そのような改革を通して、企業全体にとって新しい価値を生み出すことが期待されています。
関連記事:人事戦略の要!CHRO/CHOの役割と求められるスキルとは?
スタートアップのCxO転職の面談とフォローのリアル
スタートアップへの幹部転職支援に豊富な実績を持つBNGエグゼクティブサーチでは、スタートアップのCxO/幹部にキャリアアップした方々の豊富な口コミを公開しています。自分のキャリアをベンチャーで活かしたいと思った方は、こちらから!
部長と課長の違いとは
部長と課長は、ほとんどの企業にとって一般的な役職です。ここではそれぞれの立場や責任、業務内容の違いについて解説していきます。
立場
一般的な企業において、部長という役職には「企業の経営の一部分を担う」役割が期待されています。
一方で課長の立場は、部長とは異なり「現場のトップ」です。企業の経営方針や目標に従って、自分の所属している部署や持ち場をどのように動かすべきなのか考えるのが、一般的な企業における部長の役割になります。
責任範囲
課長はあくまでも現場サイドの管理職であるため、責任範囲も自分が所属している部署のみです。
一方で部長の場合は、会社の経営層側に属しているため、上司として部署全体の責任を担うことになります。また組織全体の成長や業績を向上させるための役割も担っているので、課長と比べると責任範囲はかなり広いと言えるでしょう。
業務内容
部長の業務内容は、取締役などの経営層と連携を図りながら、企業が適切に運営されるようにサポートをすることです。組織の成長を助ける役割を果たしながら、時代に合わせた新しい事業や企業としての成長戦略を考えることも期待されます。
一方で課長の業務内容は、現場のトップとして部署が掲げている目標の達成や現場が円滑に運営できるようにすることです。部下とコミュニケーションを取りながら、経営層から求められていることを部署がこなせるようにする役割を担っています。
関連記事:MBO(目標管理制度)とは? 実装手順から運用するメリットまでご紹介!
あなたの職歴。スタートアップ企業の幹部候補かも
現在の会社でキャリアを積んできそろ転職したいと思っているそこのあなた、スタートアップ幹部への転職を検討してみませんか?スタートアップのCxO/幹部にキャリアアップした成功者5名の実例から、スタートアップでの成功に必要なスキルや考え方、そして克服すべき課題などを学びましょう!
部長が行う業務内容
企業の経営の一部分を担うため、部長の業務内容は多岐に渡ります。
実際にどのような業務を行うのか、部長の具体的な業務内容について以下で詳しく見ていきましょう。
将来はCxOで活躍したいと考えている方へ
部内の全体管理
部長として部内の全体管理を適切に行おうとした場合、上司として次のような業務を日々こなす必要があります。
- 部下の評価と適材適所の人材配置
- 売上や利益などの数値管理
- 目標に対する進捗確認
企業の規模によっても異なりますが、数十人から数百人所属している部内の全体管理を上記業務をこなしながら行わなければなりません。
リスクマネジメント
数十人から数百人所属している部内の管理を行う部長は、その部署のあらゆる責任を負う役割もあります。
そのため、部内全体のリスクマネジメントを徹底することも部長に求められる仕事の一つです。
将来起こりうるさまざまなリスクを想定しながら、何が起きても対処できるように部内に所属している人たちの業務を管理する必要があります。
また所属しているメンバーに対してコンプライアンスの徹底を促し、何かトラブルがあった時には適切に対処できるように、的確な指示や事前準備を行うことも部長の果たさなければならない役割です。
他部署、社外との交渉・調整
部署の代表として、他の部署や社外の取引先との交渉や調整を行うのも部長の業務の一つです。
仮に他の部署と利益が相反してしまう場合は、部署を代表して他の部署と交渉を行ったり、取引先との交渉や何かあった時のトラブル処理を行ったりするのも部長の役割となります。
経営戦略の浸透と実行
部長は、経営戦略を一般社員へ浸透させ部下が実行できるように促す役割を担っています。
そのためには部長自身が企業全体の経営戦略を理解して、自分の管轄している部内の一般社員たちへ伝達・浸透しなければなりません。
また新規部署を立ち上げる場合には、経営戦略の浸透と実行だけではなく、企業として新しい価値を創出することも経営陣から求められます。
働きやすい職場環境をつくる
部長は、自分の管轄している部内に所属する一般社員の人たちが、働きやすい職場環境を作ることも業務の一環として求められます。
働きやすい職場環境を作ることによって、部内全体のモチベーションや生産性が向上したり、従業員が早期退職することを防いだりすることが可能です。
また職場環境の改善だけではなく、部下一人ひとりのメンタルケアをすることも、部長職に求められる役割となります。
長期的な人材育成
長期的な視点から人材育成に取り組むことも、部長が行わなければならない重要な業務です。
自分が管轄している部下が成長すれば、日々の業務で高いパフォーマンスを発揮できるようになり、企業としての目標を達成するために必要不可欠な人材となります。
そのためには長期的な視点から、適材適所で部下に対して仕事を割り振り、段階的に成長できるようにすることが重要です。時には必要なスキルや知識を習得させるために研修を行うこともあるでしょう。
関連記事:チームマネジメントとは?必要とされるリーダー像と成功のポイント
有名スタートアップのCxO・幹部になるには?
800名以上の幹部を送り出してきたBNGは、スタートアップ業界では圧倒的な存在感のあるエグゼクティブサーチで30代後半から40代後半までのキャリアアップ成功事例が多数あります。BNGへの無料登録であなたにマッチしたオファーが!
部長に求められるスキル
経営の一角を担う存在としてさまざまな業務をこなさなければならない部長は、一般社員や課長などとはまた違ったスキルを求められます。
部長として成功を収めるためには、どのようなスキルが必要なのか以下で詳しく見ていきましょう。
意思決定力
意思決定力とは、複数の選択肢の中から適切なものを選ぶことのできる能力のことです。
数十人から数百人の人たちで構成されている部署を管理する部長は、あらゆる選択肢の中から適切なものを選べる意思決定力を求められます。
自分が置かれた環境の中で正しい決断を下せるようになるためには、推論力や直感力、問題解決能力などを日頃から鍛えなければなりません。
業務マネジメント能力
部長は、企業全体の目標や戦略から部署が達成しなければならないゴールを逆算して、そこに至るまでの過程を構築する能力が求められます。
具体的には、PDCAサイクルを日々回して、部内の人たちそれぞれが目標を達成できるようにサポートしなければなりません。
そのためには部内全体を俯瞰して見ながら、課長や一般社員の人たち一人ひとりを細かく見る2つの視点をもつ必要があります。
人材マネジメント能力
部長は直属の部下となる課長や一般社員に対して、自発的に動けるよう日々教育を行う必要があります。
また長期的な目線で、課長や部長候補となるであろう人材を選び、将来的に管理職として働けるようさまざまな能力を身につけさせることも部長に求められる役割です。
リスクマネジメント能力
数多くの人たちが所属している部署では、日常的にさまざまなミスが起きることも予測されます。場合によっては大きなトラブルに発展することもあり、そういった場合の対処法や事前にトラブルを防ぐための対応策等を教育することも重要です。
そのため部長職として活躍するためには、業務をこなすだけではなく、部下に対してリスクを周知したり、トラブルが起きた時にどうすればいいのか事前に教育したりするリスクマネジメント能力も求められます。
コーチングスキル
コーチングスキルとは、会話や問いかけなどから相手の思考を刺激して、答えや意欲などを引き出す能力のことです。
部内のメンバーや課長の能力を引き出し育成するためには、部長から一方的に指示やアドバイスを行うのではなく、それぞれから意見を引き出し・聴くことが求められます。
コーチングスキルにおいて重要となるのは、相手の意見を傾聴して質問することです。一般的な企業の部長職に就任した人であれば、一般社員や課長を経験している間に「伝える」というスキルはある程度身につけているでしょう。
それに加えて部長職では、相手から引き出すことのできるコーチングスキルも必要となるのです。
関連記事:メンタリングとは?コーチングとの差、メリット、実施方法を解説
スタートアップのCxO/幹部になって責任に見合う報酬を!
登録者数40,000人突破したBNGエグゼクティブサーチでは、スタートアップのCxO/幹部になって責任と成果に見合った報酬を獲得したキャリアアップ事例をご紹介しています。コンサルタントへ...
まとめ
部長は課長などと比べると責任範囲も広くなり、抱える人材も多くなるのでマネジメントに多大な労力がかかります。
しかしその分経営層に近いところで意思決定ができるので、会社の成長に貢献しつつ自分自身の成長も実感することができるなどさまざまなメリットがあるポジションです。
もし部長職を目指しているのであれば、BNGパートナーズを利用して経験豊富なエージェントに相談するのがおすすめです。