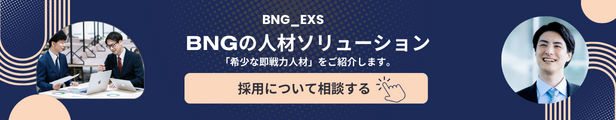「日本酒の未来をつくる」をビジョンに掲げ、ラグジュアリー日本酒ブランド「SAKE HUNDRED」を運営する株式会社Clear。社員数20名前後のスタートアップながら、日本酒における高価格帯市場を切り拓き、業容を拡大させています。同社が目指しているのは、「SAKE HUNDRED」をグローバルラグジュアリーブランドとして確立すること。それが、業界に大きな価値をもたらすと信じているからです。そのためにも、資金調達や採用活動に積極的に取り組んでいます。
同社の代表取締役CEO、「SAKE HUNDRED」ブランドオーナーとして数多くの魅力的なプロダクトを生み出し、日本酒産業に希望の光をもたらしているのが生駒氏です。まさに、業界のイノベーター・革命児と言えます。「会社経営の本質の一つは、約束事を決め、それを守ること」と力説する生駒氏が、ビジョンの実現に向けてブランド戦略を組織・採用戦略に落とし込んでいくために何が必要だと考えているのか。BNGパートナーズエグゼクティブサーチ事業部長として、あらゆる採用の最前線に精通した岡本勇一、コンサルタントの高島琉衣が対談を通じて、紐解いていきます。前編では、生駒氏と日本酒との運命的な出会いやブランディングの意味合いにフォーカスします。
リーダークラスのための転職サイト
BNGパートナーズは30代から40代のリーダー・課長クラスの方々の転職も支援しています。有名スタートアップから上場メガベンチャー企業まであなたの経験を必要としている求人案件をご紹介します。
ある日本酒との衝撃的な出会いが、僕を起業家へと導いた
高島:まずは、生駒様のご経歴と起業の経緯をお聞かせいただけますか。
生駒:大学卒業後、1年半ほどIT企業で働いた後に独立し25歳の時に、日本酒の魅力にはまり、「これを仕事にしたい」と決意し、この世界に身を投じました。
2013年2月にClearを設立し、2014年にSAKETIMESをローンチするなかで
日本酒の価値をより強く確信し、それが世界で認められるという想いが強くなり、日本酒ブランド「SAKE100」(現在の「SAKE HUNDRED」)を創業し、世界に出て行こうとしている段階です。
高島:日本酒への情熱に駆り立てられたきっかけは何ですか。
生駒:大学の同級生が、室町時代から続く酒屋の息子でした。その彼が実家を継ぐこととなり、「今後はインターネットを通じてお酒を売っていきたい」という相談を受けたのがきっかけでした。
ただ、僕は元々お酒に弱く、一杯ぐらいしか飲めませんでした。彼から「お勧めの日本酒を一本持っていくので試しに飲んでほしい」と言われました。
それが、熊本県酒造研究所の「香霧」という日本酒でした。本当に美味しくて衝撃が走ったんです。僕が持っていた日本酒のイメージを完全に覆してくれました。
それで、日本酒に興味を抱き調べてみたところ、国内市場が小さいものの昨今は蔵元の代替わりがあって、若手の動きが活発になっていることがわかり、なおかつ、グローバルで伸び始めていたんです。
その割には、マーケティングやインターネットの活用が後手に回っている業界だったので、アップトレンドに持っていけるのではないかと思い、決心したという流れです。
日本酒の可能性を確信。スタートアップとして高級路線に挑む
岡本:初歩的な質問で恐縮ですが、グローバルで言うと、日本酒はどんな立ち位置なのですか。
生駒:まだまだ無名のアルコール飲料です。輸出の規模も410億円ほど(2023年実績)しかありません。
ワインは世界全体だと40兆円ですから、比較になりません。その一方で、フランスで一流のレストランのシェフやソムリエのトップ層が、日本酒の価値を高く認めてくれています。そこに良い兆しを感じています。
高島:「SAKE HUNDRED」をスタートされて5年が経過しましたが市場の変化はいかがですか。
生駒:2018年に「SAKE HUNDRED」を創業した当初は、「高級酒市場にはチャンスはあると思うが、実際にはどうなのか」という声が多く、産業全体の認識としては靄が掛かった状態でした。
業界関係者から「日本酒に1万円、2万円を出す人はいない」というフィードバックをもらったこともあります。
そのため、消費者の意識改革だけではなく、産業従事者の意識改革も必要だと思い、僕は色々な酒蔵さんに足を運んで話をしたり、レストランに営業に行き価値や美味しさを伝えていきました。
5年経ってどうなったかと言うと、高級酒が続々と出て来ています。しかも、価格は僕らとほぼ同額のものもあったりします。それは素直に嬉しいです。
カテゴリーや市場の成熟は1社だけでは意味がないですからね。
色々な企業が参入し、認知が広がって初めて高級日本酒というカテゴリーが成立します。
だから、物凄く手応えを感じています。同時に産業側の意識が非常に前のめりになってきたのもポジティブな手応えの一つです。
高島:酒蔵の方々の日本酒に対する価値観については大きな変化を起こせたと感じておりますか。
生駒:酒蔵さんにもよりますが、やはり家業だとリスクを背負うのは、難しいものです。
「イケる」とは思っていても、懐疑的になっている方も見受けられます。
本来なら、挑戦によって証明すべきなのですが、酒蔵さんは親から受け継いだ経営のバトンを次の世代に渡すことが使命ですからね。要は、潰せないということです。そう思うと、何か大きなリスクを背負って一か八かみたいなことはやらないです。
一方、スタートアップは背負うものがありません。突き進むしかないので、そこは僕らが彼らの代わりにできる役割であるということです。
リーダークラスのための転職サイト
BNGパートナーズは30代から40代のリーダー・課長クラスの方々の転職も支援しています。有名スタートアップから上場メガベンチャー企業まであなたの経験を必要としている求人案件をご紹介します。
ブランドは生き様によって作り出される
岡本:生駒様にとってのブランディングとは何ですか。どんな定義で捉えているのか。それが今後の御社の戦略にどう乗って進んでいくのかが気になります。
生駒:ブランディングとは、教科書的に言うとお客様の中に想起されるイメージです。
つまり、我々のものではないということが大前提にあります。なので、僕らが幾ら「こういうお酒です」と言っても、お客様が「何か違うな」と想起してしまうと、それはブランディングができていないということなのです。
特に僕らは、「SAKE HUNDRED」をラグジュアリーなブランドと謳っています。
お酒を飲んでもらった時にそれに相応しいイメージをお客様に持ってもらえないとすれば、僕らの行動が間違っていることになります。
言っていることとやっていることが一致しているからこそ、顧客の中のイメージもその通りになります。自分たちが思い描いていることとお客様のイメージを一致させることがブランディングだと思います。
ブランド作りをどうするかは難しいものです。まるで人作りのように多面的なものです。
360度どの角度から見ても、そのブランドらしさが出ている。どの瞬間でも筋が通っているというものを作れるかどうかだと思います。
それは、僕自身が「ブランドには長く関わっていかないといけない」と言い続けている理由でもあります。結局、言っていることとやっていることが、一致しているかどうかは生き様で証明するしかないんです。時間を掛ければ積み上がっていきます。だからこそ、やりがいがあるのです。
僕らは自分たちの美しさや正義、格好良さを積み上げていけば、「SAKE HUNDRED」が絶対世界に通じると信じています。
なので、それらをとにかく研ぎ澄ませていく。それがブランディングだと位置付けています。
岡本:ラグジュアリーブランドとして見られたいというのは、一つの側面でしかないと思います。何を生き様として見せたいと考えているのですか。
生駒:「SAKE HUNDRED」と出会うことによって「人生が楽しい」「生きていて良かった」みたいな気持ちになってもらえたらと思います。
僕らは、そういう人間の感情を揺さぶる仕事をしているんです。人生の揺らぎを与えてくれるのが、お酒ですからね。「SAKE HUNDRED」を通じて感情のポジティブな揺らぎが生まれて、ラグジュアリーだと感じる豊かな時間を過ごしていただければと思います。
ラグジュアリーはマーケットのアプローチ法でしかありません。
お客様にはシンプルに生きることを肯定してほしいんです。それを僕らは「心を満たし、人生を彩る」というブランドパーパスとして表現しています。
その想いを伝えたいと思っています。
言動を一致させ続けること。お客様への約束は守る
岡本:ブランディングを事業成長に紐づけるには、どうしたら良いとお考えですか。
生駒:言っていることとやっていることを一致させるに尽きると思います。格好良いことを言うのは誰でもできます。
でも、実際には「それって合っていないよね」みたいなことがあったりします。
言葉に対して品質が追い付いていないんです。それこそ、不一致だと思います。
それは、マーケティング的にもうダメなんです。
とにかく、ブランディングにとって大事なことは言動を一致させ続けることです。
ブランドサイトで、「お客様に豊かな体験を提供します」と謳っているのであれば、それを守り続けないといけません。もちろん、これは僕らにも言えることです。
そこが一番ではないでしょうか。お客様に言ったことは、約束事です。
だから、それを守らないといけないのです。
岡本:どのような壁を乗り越えてきたことで、ブレークスルーが来たとお考えですか。
生駒:何か一つのきっかけがあったというよりも、色々なものが降り積もった結果としてのブレイクスルーだと思います。
とはいえ、幾つかの大きな要素も持っているため、三点ほど挙げたいと思います。
一点目は、定性的なブランド評価を上げることに注力したことです。
ブランドの設立から3年目ぐらいのタイミングで売上が20億円まで伸びました。
そこに至るまでの2年間で何をして来たかというと、海外のコンペティションに応募して金賞を獲得したり、G20関連カンファレンスの乾杯酒採択に働きかけたり、都内のラグジュアリーなホテルのレストランに、僕らのお酒を採用してもらえるよう営業を掛けていました。売り急がず、地道に活動したということです。
二点目は、2020年のリブランディングです。
「SAKE100」から「SAKE HUNDRED」に表記を変えただけでなく、自分たちは何者かを考え抜き、お客様に提供する価値や体験を徹底的に考えました。ブランドステートメントを見直し、新たなメッセージを策定しました。また、価格帯も大幅に上げたり、ラベルも刷新しました。理想のお酒は造れたのにも関わらず、実態が見合っていなかった部分を見直したんです。
当時はラグジュアリーではなくプレミアムと銘打っており、お客様からは「値段やクリエイティブのレベルが中途半端でギフトとしては送りにくい」との指摘もありました
三点目は、新型コロナの感染拡大です。これによって内食ニーズが上がり、ECサイトの売上も大きく伸びました。
岡本:様々な要素の効果を掛け合わせた結果、ブレークスルーが起こったのですね。
続いては、ブランド戦略を組織内に浸透させるポイントについてお伺いさせてください。
後編へ続く
前編では「生駒氏と日本酒との運命的な出会いやブランディングの意味合い」についてお伺いしていきました。後編では「ブランド戦略を組織内に浸透させるポイントや今後の事業展望」についてクローズアップしていきます。
Clear社のような新たな市場を開拓するベンチャー・スタートアップ企業にご関心のある方はBNGパートナーズに登録してみませんか。
BNGパートナーズでは、ベンチャーCxOなど、ハイクラス・高難易度な採用を支援する「ベンチャー × 経営幹部」に特化した人材紹介を行っています。
40,000人を超えるエグゼクティブ・ハイクラス人材の中から、企業カルチャーにマッチした人材選定をいたします。採用においてお悩みであれば、まずはBNGパートナーズお問合せ窓口からご相談してみてください。
企業の人事担当者・責任者の方へ
BNGパートナーズは、ベンチャー企業やスタートアップのハイクラス人材に特化した転職サービスを提供しております。スタートアップへの転職を検討しており、より高みを目指せる場所に身を置きたい人は、BNGパートナーズの転職サービスをぜひご活用ください。
将来はCxOで活躍したいと考えている方へ